「もてなし」・「もてなす」の出典、源氏物語と村山リウ
「もてなし」(名詞形)の初出は、日本国語大辞典によれば『源氏物語』「若紫」とあります。『源氏物語』は、現代語訳・注釈・意訳・超訳・説きがたり・マンガ・翻訳に至るまで、時代を反映しながら様々なジャンルの作家が紐解き、~源氏と呼ばれ、途切れなく読み継がれている一方で、同辞書には、最初の「桐壺」の巻で読むのをやめてしまう「桐壺源氏」の言葉も挙がっています。
現代語訳では、与謝野源氏・谷崎源氏・円地源氏・田辺源氏・瀬戸内源氏・林(望)源氏・角田源氏、また小説として独自の再構築を試みた林真理子らの作家が知られており、その中に村山源氏があります。
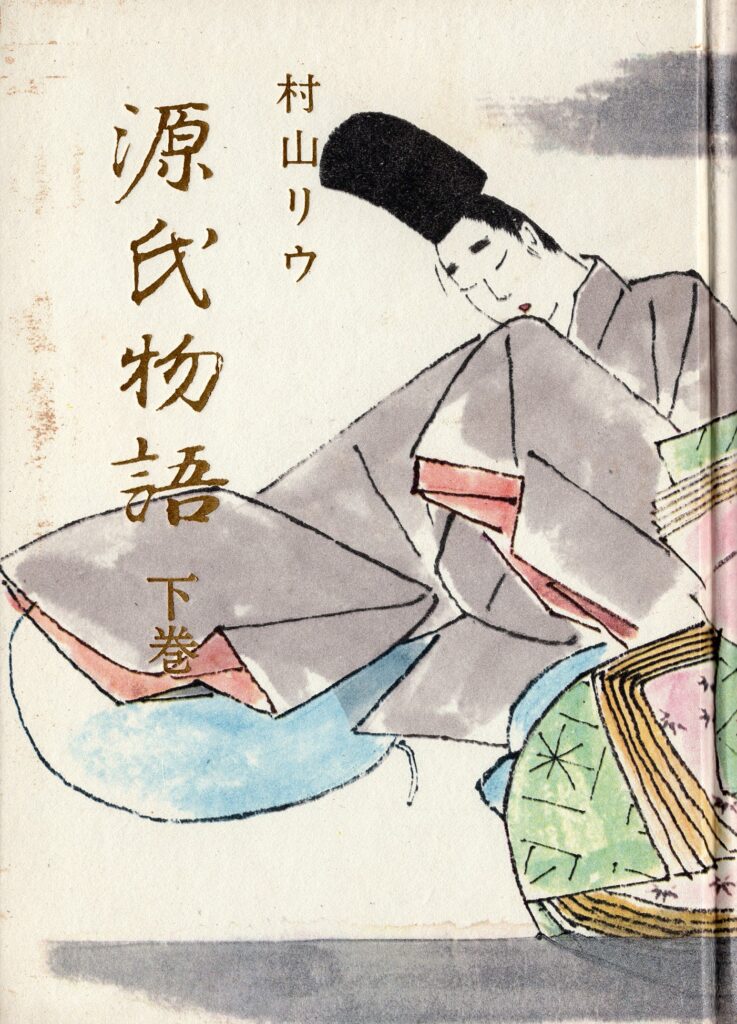
図1 村山リウ 昭和44(1969)年 新装初版『源氏物語 下巻』創元社 装画 中村貞以 表紙
(表・裏表紙写真は創元社に許可をとり掲載しています。筆者所蔵古書のため、写真は上中下巻の中で、少しでも保存状態がよいものを選んでいます。)
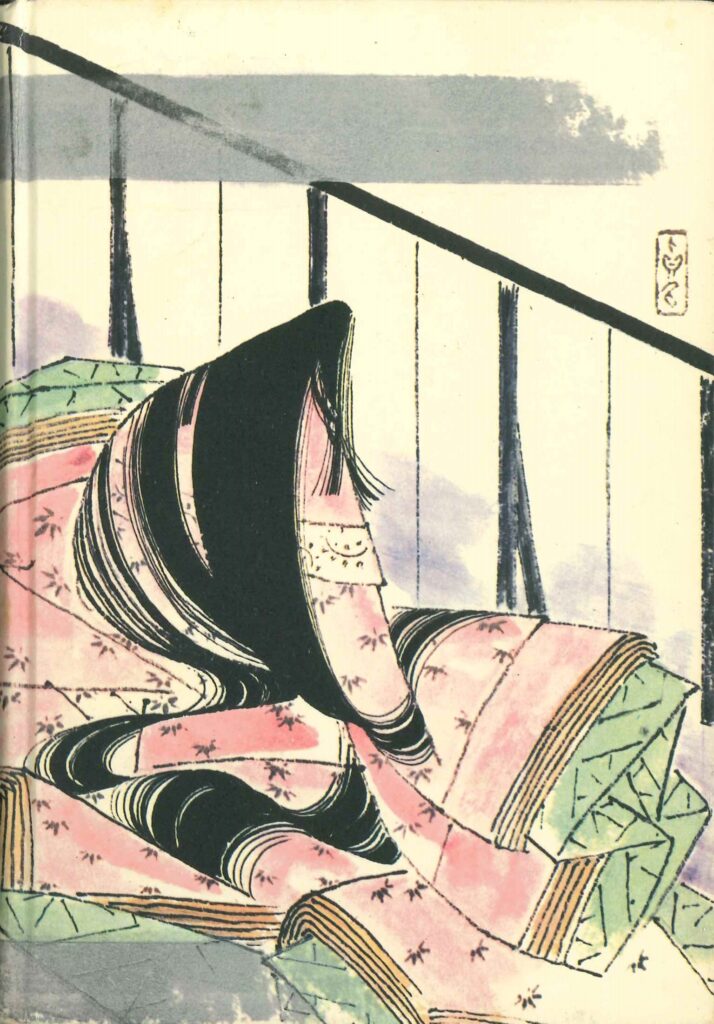
図2 村山リウ昭和50(1975)年 新装5版『源氏物語 上巻』創元社 装画 中村貞以 裏表紙
説きがたりとして源氏を語り綴った村山リウ(1905‐1985)は、明治3(1905)年、古くから信仰と観光名所でも知られる金刀比羅宮がある讃岐・琴平の天領であった榎内(えない)村で生まれました。本学が讃岐で開学したこと、また「もてなし」の初出が源氏物語でもあることから、村山リウに関して最初に少し触れておきます。以下、村山リウ自身の著作である『私の歩いた道』(創元社)、『私の中の女の歴史』(人文書院)、『女の自立』(大阪府)を資料とします。
リウの父、織田栄五郎は瀬戸内海の小さな島生まれで、当時善通寺の第十一師団(野木希典が初代師団長)に所属していた軍人でした。母、天留(てる)は代々金刀比羅宮のお山侍で棟梁の家であった斎藤家の出身で、リウは、旧暦上巳3月3日(新暦4月1日)に生まれました。その名リウの由来も、讃岐では雛壇を床の間の真ん中に飾り、床柱の下の方に桃の花を生け、その反対側から芽ぶきのしだれ柳に餅花をつけて飾る習慣から、「柳」と書いて「リウ」と名づけられたとあります。4歳からは、父の第十七師団への転勤に伴い岡山で暮らし、岡山県立第一高等女学校から、現在の日本女子大学国文科に進学します。医師との結婚を経て、評論家・女性活動家として頭角を現しますが、自分にとって「本当だったこと」として源氏を語ることを長年続けました。明治・大正・昭和と生きた時代の中、「年というものは隅を照らす力を養ってくれる」と表現しつつ、戦後間もない時期から、婦人たちを対象に輪読のような形で源氏講義を始めています。
村山源氏『源氏物語 上巻』(昭和35(1960)年初版)序の書き出しは、「源氏物語は九百五十年前、一条天皇の中宮彰子の教養顧問として奉仕していた紫式部が書いた、幽艶でかぐわしい長編小説であることは言うまでもありません」とあり、紫式部が出仕中に書いた物語は、「仮名は女文字として軽蔑されたおかげで、文学の世界にだけ女性の意思表示の自由を見出すことができた」成果でもありました。また下巻「解説」では「兄惟規(のぶのり)が史記を学ぶのをそばで聞いていて兄よりもよく覚えた」とあり、藤原為時の女として生まれた紫式部は、幼い頃から聡明で、和漢両様の博学でありました。1001年から1010年頃の平安時代、仮名文学の傑作として、世界でも類を見ない長編文学が生み出され、その頃すでに使われていた「もてなし」の言葉があったことは、初回の「はじめに」でも記しました。和漢の深い学識教養により綴られた物語の中での「もてなし」は、その品詞、使われている帖、文脈により「身のこなし」・「ご様子」・「嗜み」・「取り計らう」など現代語訳も様々ですが、平安時代の貴族たちの生活を映し出す多くの場面で使われています。
『源氏物語』からの「もてなし・もてなす」の言葉を、時代を映しだす言葉と捉えるならば、時代が下り江戸時代の国学者、本居宣長(1729 -1801)は、その源氏自体を「もののあはれ」を表現した作品と位置づけました。村山リウは「下巻」解説で、「『もののあはれ』と本居宣長がいみじくも表現したのは、源氏物語の中に語られている日本的まごころであり、人間性の奥深く魂のふるさとを思慕する物語の情調を言う」と綴っています。本居宣長は、伊勢の国松坂(現在は阪の字)の人で、筆者も同郷であることから最後に少し補筆します。
この「あはれ」の言葉は、『日本古典対照分類語彙表』では、『源氏物語』内で944回という高い使用頻度です。和歌に親しみ、源氏物語を講義し、古事記伝執筆を成しとげた本居宣長による「もののあはれ」の概念は、村山リウの指摘にある「日本的まごころ」として、宣長の考証の先にあったものでしょう。本居宣長は、教える側としても日本全国に多くの弟子がおり、紫式部もまた中宮への進講という役目を担っていました。「もてなし・もてなす」や「あはれ」「もののあはれ」の言葉は、その時々の最先端で言葉と人間を大切に扱った感性豊かな人々によって、今日にもたらされた賜物であると言えましょう。

